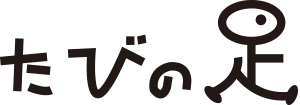福祉タクシーと介護タクシーの違いとは?
2025/07/14
福祉タクシーと介護タクシーの違いとは?車椅子のまま乗車できたり、乗降時に介助を受けられたりと、高齢者や身体が不自由な方の移動を支えるのが「福祉タクシー」や「介護タクシー」です。名前は似ているものの、実は運転手の資格や使える制度、利用できる人の条件などに明確な違いがあります。それぞれの違いを正しく理解しましょう。
福祉タクシーと介護タクシーの基本概要
高齢者や障がいのある方の外出支援として注目される「福祉タクシー」と「介護タクシー」は似たようなサービスに見えますが、介助内容や利用条件、保険適用に違いがあります。ここではそれぞれの特徴を整理していきましょう。
福祉タクシーとは?

福祉タクシーは、正式には「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」と呼ばれています。福祉タクシーは運送事業なので、一般のタクシー事業者と同じく国土交通省の管轄です。
福祉タクシーとは、道路運送法第3条に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送のことをいう。
タクシー業界では、高齢者や障がい者など手助けが必要な利用者の外出支援サービスを「福祉輸送サービス」「ケア輸送サービス」などとも呼んでいます。
介護タクシーとは?

介護タクシーは、正式には福祉輸送事業限定の一般乗用旅客自動車運送事業に該当する、国土交通省の管轄です。ただし、介護保険が適用される場合は厚生労働省も関与します。呼称は同じですが、実際には介護タクシーが使える「介護保険タクシー」と介護保険が使えない「介護タクシー」の2種類があり、区別されることがあります。また、福祉タクシーや介護タクシーでは付添人の同乗は可能なものの、介護保険タクシーでは自治体の許可が必要で、原則不可とされる場合もあるので注意しましょう。
なお、介護保険の対象となる「介護保険タクシー」の運転手には、介護職員初任者研修という介護資格も必要です。これは介護として働くうえで基本となる知識や技術を習得するための研修で、この資格を取得しておけば運転だけではなく介護利用者の身体サポートも可能となります。

車両や設備の違い
福祉タクシーと介護タクシーでは、利用できる車種や搭載されている設備に違いがあります。移動をサポートする点では共通しているものの、車種や設備も異なりますので、しっかり把握しておきましょう。
福祉タクシーの主な車種と設備
福祉タクシーでは、車椅子やストレッチャーのまま乗車できるように、ワゴン型・ワンボックスタイプの車両が多く使われています。電動リフトやスロープ付きで、利用者の負担を軽減してくれるのが特徴です。ただし、乗降の介助は家族やヘルパーの同行が必要な場合もあり、タクシー会社によっては介助ができないケースもあります。最近では、天井が高く車椅子に対応した一般タクシーもあり、予約不要で利用可能なものの、障がいの程度によっては事前相談が望ましいです。
介護タクシーの主な車種と設備
福祉タクシー同様、介護タクシーに使われる車両は利用者に負担がかからないように乗車できるものです。ワゴンタイプやワンボックスタイプが多く、車椅子やストレッチャーから降りずにそのまま乗車できる電動リフトや、足が不自由な方や歩行が不安定な方も安心して乗降できるスロープなどが整っています。

利用できるサービス範囲や対象者の違い
福祉タクシーが対応する対象者と用途
福祉タクシーは「営業所において運送の引き受けを行う輸送に限る」というルールがあるため、一般のタクシーとは異なり事前予約が必要で、道路で手を挙げての利用はできません。
福祉タクシーの利用対象者は、以下のようになっています。
- 身体障害者手帳の交付を受けている者
- 要介護認定を受けている者
- 要支援認定を受けている者
- 上記①~③のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害やその他障害により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
- 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
出典:一般乗用旅客自動車運送事業について(福祉輸送事業限定)
上記からも分かる通り、福祉タクシーは身体障がい者の方や身体の不自由な方の移動をサポートする車両です。そのため、高齢者のみなどといった利用制限はありません。付き添いの方も同乗可能で、利用目的も通院や買い物、レジャーなど自由です。ただし、運転手に介助を依頼する場合は、別途介助料がかかることもあります。
介護タクシーが対応する対象者と用途
「介護保険タクシー」で介護保険を使うには、利用者側にもタクシー事業者側にもそれぞれ適用条件があります。なお、介護保険の適用となるのは乗降などの介助であり、輸送は含まれません。
利用者側は、ケアマネジャーが作成したケアプランに「乗降介助・身体介護が必要」と記載されていることです。要介護1以上でも介助なしで車の乗降ができる場合は、介護保険適用外となります。また、介護保険適用条件は「日常生活上または社会生活で必要な行為に伴う外出」に限られますので、プライベートな目的による利用は介護保険適用外です。
一方、事業者側が介護保険適用事業者になるためには、法人会社になり訪問介護保険事業所の指定を受ける必要があります。提供するサービスに合わせて、介護支援専門員やスタッフ、生活相談員などの必要な人員を満たさなければなりません。
両者の利用制限や条件の違い
福祉タクシーは、自治体によっては利用料金の補助制度があります。利用する際はどのような補助制度があるのか、担当窓口に問い合わせてみるのもおすすめです。また、タクシー料金を助成する「福祉タクシー券」を配布する自治体もあります。しかし自治体によって利用対象者や金額、交付方法も異なるため前もって確認しておきましょう。
| 福祉タクシー/介護タクシー | 介護保険タクシー | |
|---|---|---|
| 対象者 | ①身体障害者手帳の交付を受けている者 ②要介護認定を受けている者 ③要支援認定を受けている者 ④上記①~③のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害やその他障害により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者 ⑤消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者 |
介護認定を受けた要介護1〜5の人のみ |
| 利用制限 | なし レジャーなども可能 |
あり 日常生活において必要不可欠なもののみ |
| 移動による介助 | 介助は可能 | 乗降時の介助、乗降後の介助も可能 |
| 介護保険の利用 | 不可 | 条件を満たせば利用可能 |
| 同乗 | 可能 | ケアマネジャーに相談 |

まとめ
福祉タクシーと介護タクシー(介護保険タクシー)は移動支援を目的としたサービスですが、対象者や利用条件、運転手の資格などに違いがあります。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて使い分けましょう。
高齢者や障がい者のためのタクシーを手配するなら、貸切タクシーの専門店たびの足の一括見積もりサービスをぜひご活用ください。24時間受付のWebフォームに必要事項を入力いただければ、最短5分で無料見積もりが可能です。複数のタクシー会社からタクシーを比較できるため、ニーズに合わせて選びやすいでしょう。
WEBで簡単!無料お見積り!
-
カンタンWebフォームにて
見積・予約受付中 - お問い合わせスタート